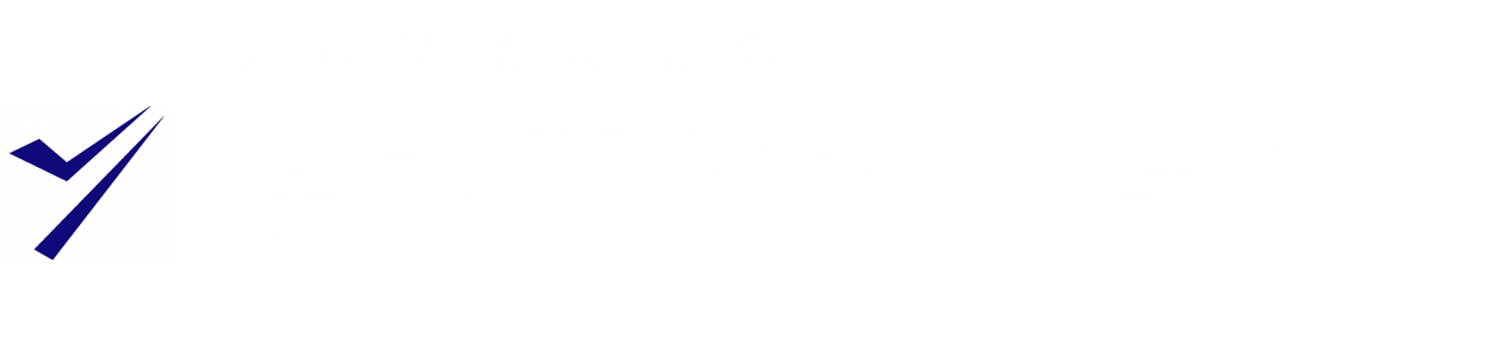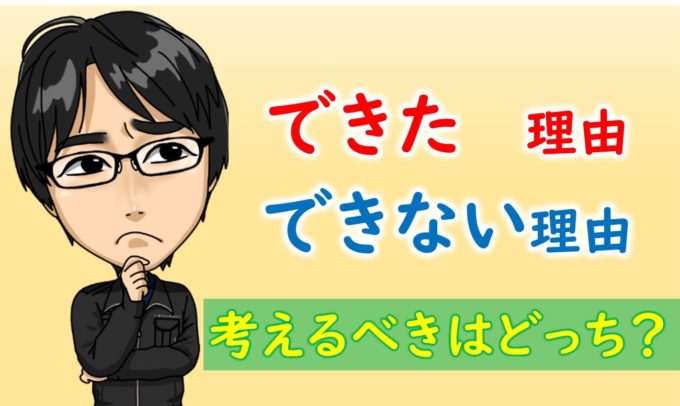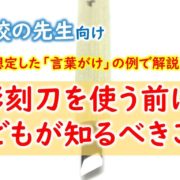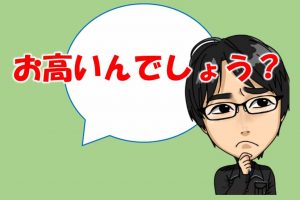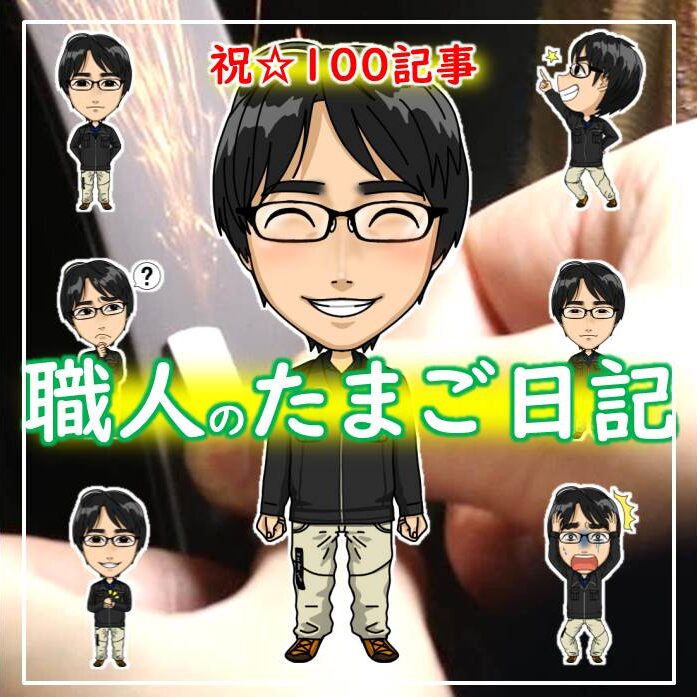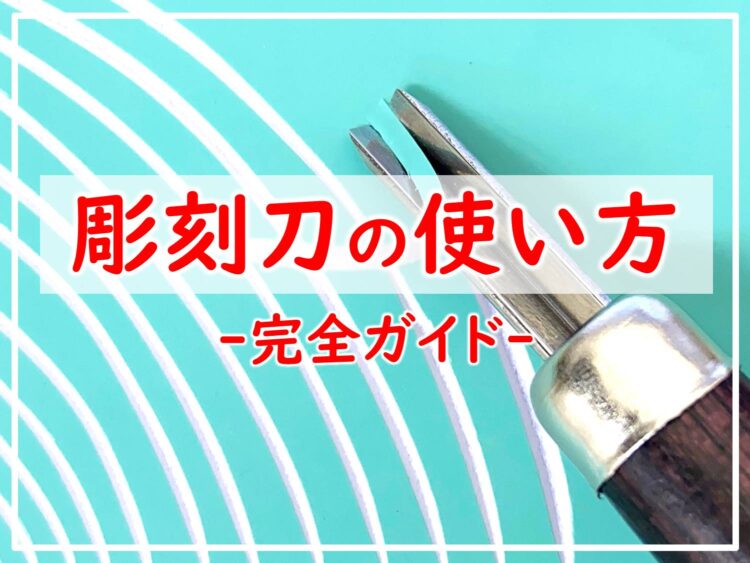うまくできないと、もどかしい。
うまくできないと、おもしろくない。
うまくできないと、ストレスがたまる。
だから、うまくできるようになりたい!
こんにちは。
職人のたまご、奥村です。
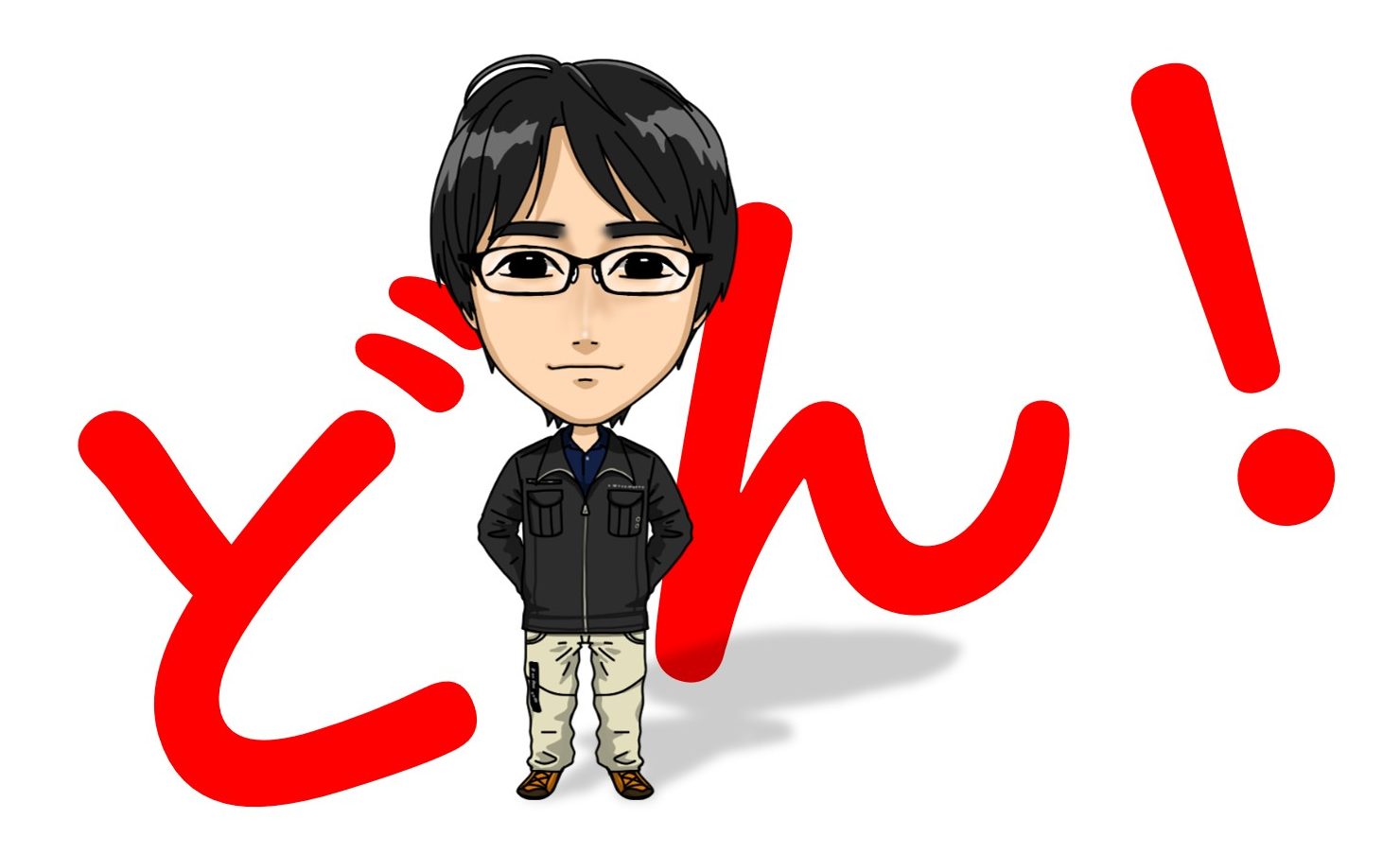
「どうやったらうまくできるのか」
僕は、常に考えながら作業しています。
そんなある日、こんな疑問が浮かび上がりました。
- 技術を習得するには、「うまくできたこと」を考えるべきか。
- それとも、「うまくできなかったこと」を考えるべきか。
単純に言うと。
- 今のはうまくいったぞ → なぜできたの?
- 今のは全然ダメだった → なぜできなかったの?
「どちらを考えたほうが、技術習得がスムーズにいくのか」
みたいな感じです。
もくじ
技術を習得するときの考え方

うまくいったとき、「なぜうまくいったのか」を考える。
うまくできなかったとき、「なぜうまくできなかったか」を考える。
技術を習得するうえで、果たしてどちらを考えるべきか?
僕なりの答えを出してみます。
まず、前提条件として。
「完全初心者は、どちらが技術をスムーズに習得しやすいか?」
という問いで考えてみます。
僕の結論は、下記のとおりです。
「彫刻刀の刃の形を整える作業」で考えてみる

(写真:高速回転するサンドペーパーで、刃の形を整える作業)
彫刻刀の刃をたくさん製造すると、刃がゆがんでいるものが出てきます。
それを職人が、高速回転するサンドペーパーに刃を当て、正しい形に削っていきます。
この作業、超難しいんです。
刃は、少しサンドペーパーに当てただけで、簡単に削れてしまいます。
なので、数秒の間に、刃の形を整えなければなりません。
かなり繊細な技術が要求されるんです。
例えば、うまくいかないと下の写真のようになります。

(写真:小丸刀の刃の形)
左側が、上手に刃の形を整えられたケースです。
右側は…悲惨ですね。
刃の形を整える技術がないと、いびつな形になってしまいます。
スムーズな技術習得の考え方
さて、ここで本題。
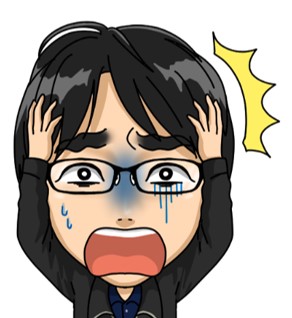
- 「彫刻刀の刃の形をうまく整える技術を習得したい!」
- でも、なかなかうまくできない…。
そこで、先ほど僕が出した結論。
技術を習得するには、反復練習が必要ですよね。
そのとき、まぐれでも上手にできるときが必ずあるはず。
「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」ですね。
その当たったときが、勝負。
「なぜ今のは、うまくいったんだろう」
当たったときに考えてみると、何かコツが見つかるかもしれません。
コツが見つかったら、即メモをします。
見つからなかったら、また下手な鉄砲を撃ち続け、当たったときにうまくできた理由を考えます。
- たくさんの練習を積み重ね、少しずつ成功体験を積み重ね、そこからコツを見つけ出す。
そのコツがたくさん集まり、塊になることで、「うまくできるようになっていく」と考えます。
まぁ、前提として、頭が熱くなるほど考え続けなければなりませんけどね。
パズルのピース
例えるなら、パズルのピースをはめ込んでいく感じ。
「技術のコツ」というピースを、地道にはめ込んでいくことで、いつかはパズルが完成します。
逆に、「うまくできなかった理由」を探ることは、完成したパズルの中からピースを取り出すような感じ。
けれどこの場合、取り出すピースを探すのに、時間がかかってしまいます。
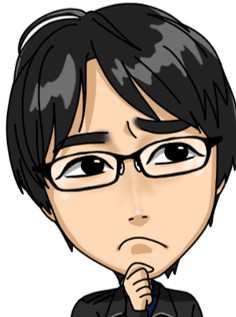
- 今のは、これができていなかったのかな?
- いや違う、こっちかな?
そもそも、完成した状態を知らなければ(技術を習得した状態が体感的にわからなければ)、どれを取り出していいのかわかりません。
結論として、パズルのピースをはめ込んでいくほうが、完成するまでの時間が圧倒的に早いのではなかろうか。
つまり、最初に戻ります。
- 技術をスムーズに習得するには、「なぜうまくいったのか」を考えると良い。
考え方は技術の習得段階によって変わる?
「なんでうまくできなかったんだろう」と考えるのは、悪いことではないと思います。
ただし、うまくできなかった原因を探るのは、ある程度技術を習得した状態になってから有効かもしれませんね。
長々と書きましたが、これが正解というわけではありません。
あくまで僕の考えとして、知っていただけたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
こちらの記事もおすすめ!